高松大空襲の日から
磯海 瑠美子(執筆当時 高倉中学校)
昭和27年7月3日と8月15日を語るとき、私は9歳の昔に戻るのです。
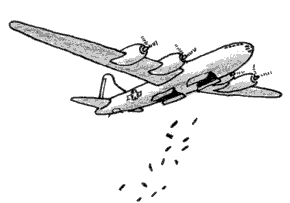
3日は、星の美しい夜でした。あの夜も「空襲警報」はB29と共にやってきました。小学校3年生の私はぐずりながら身支度をして、庭向きの縁側に腰掛けていました。防空頭巾をかぶり、水筒と乾パンと救急薬の入った袋を左右の方から下げ、モンペ姿でした。B29はドロドロドロ……と不気味な低温を発しながら頭上を飛んでいきます。聞き慣れた音ですが、今夜はいつまでもそれが続くのです。いくついるのかな、林の飛行場へ行くのかなとぼんやりそんなことを考えていた時です。ドドーンと体中、揺すり上げられるような音と共に、瓦町あたりの空が真っ赤になりました。
「爆弾が落ちたんや。ここにおったらいかん。にげよう!」
19歳の叔母は叫ぶと、私と祖母の手をつかんで走り出しました。大きなリュックを背負った叔母は、今の私の娘の年齢です。女学校の専攻科から挺身隊として、軍需工場へ飛行機を作りにでかけていました。すでに、隣組の防空壕は人でいっぱいです。
「この中に入ったら、かえって危ないわ。走ろう!」
この叔母の判断が正しかったことは、後日わかりました。家を出た直後、2発目がすぐ後ろで炸裂しました。後でわかったことですが、山に逃げ込むことを想定して、敵機はまず山を包囲したのです。紫雲山の麓に住んでいた私は、追われ、追われすることになったのです。すでに栗林公園は火の海でした。爆発音と悲鳴の中を突っ走りました。
「お母さん!」
と叫ぶ子ども。我が子の名前を呼ぶ母親。何度も伏せながら走りました。配給でもらった運動靴の片方は茨の垣根に消えました。動物園の前まで来たときです。ここは広場で身を隠すところがありません。
照明弾が落とされました。昼間のように明るくなった中に頭上の敵機のマークがはっきり見えたのです。星形のマークは記憶にありました。運動会の玉当てゲームで的になったルーズヴェルトかチャーチルの胸にでもついていたのでしょうか。この時ほど恐ろしいと感じたことはありません。
私たちは南へ南へと走りました。ひたすら走ったのは、この夜の爆撃がほとんど焼夷弾だったからです。叔母は、
「焼夷弾は直撃されなければ大丈夫。頭の上で分かれたらすぐ後ろへ落ちるはず。」
どこで聞いて知っていたのか。そんなことをいうのです。でも、大きな一つの爆弾から何十本もの焼夷弾が分かれ、雨のように降ってくる、それが頭の真上なら生きた心地のするはずがありません。ところが叔母のいうとおりになるのです。私たちのすぐ後ろを追いかけてくるように落ちました。シュルシュルーッ、次いで火柱が上がり、炎が辺り一面這うのです。水田の面を走る炎は、逃げ込んだ牛の体にくっついていきました。途中、藪の陰に身を寄せている兵隊さんの一団を見ました。それは教科書の中で見る勇ましい格好でなくまるで隠れているようでした。不思議でなりません。敵機のはるか下方で、ブスッブスンと途切れる高射砲の煙…。かれこれ、4時間近く走った勘定です。円座村の成合橋の上で昇ってくる赤い大きな朝日を見ました。それが血の色のような暗赤色をして、異様な大きさであったことを覚えています。
二日後、叔母は様子を見に高松に帰りました。家は跡形もなかったこと、海まで見える程、一面焼け野原であったこと、同じ隣組のブリキ屋さん一家は、警防団員であったお父さんひとりを残して、7人があの私たちが覗いた防空壕で蒸し焼きになったこと、センバ川は死体でうまってしまっていたこと…などをその夜聞きました。何より驚いたのは、私たちがいた庭に焼夷弾が3本も突き刺さっていた話です。庭で走る中で、私たちはわずか何分、何十メートルの差で、かろうじて命が助かったのです。
円座村から親類を頼って川東村へ。そこで、疎開生活が始まりました。空からはB29に替わって艦載機の機銃掃射に追われるようになりました。学校まで1里もあるので、途中で空襲警報になることもしばしば。そのうち、公民館やお寺が臨時の学校に替わりました。先生は出張授業です。艦載機はほとんど毎日やってきて、村人たちを追いかけます。栴檀(せんだん)の大木の周りを逃げ回った野良帰りのおじいさん、小さい子を追いかけて撃ったタマは、とうとうその子のお母さんの命を奪いました。すべて狭い村でのできごとです。艦載機は、キューン、ヒュルヒュルという音と共に、相手かまわず怪鳥のように襲いかかりました。
8月15日、男の人がやってきて、
「今日は、水車屋(米屋さん)で大事な放送があるんや。ぜひ来てな。」
小さな村のこととて、ラジオがあるのは、ここぐらいなもの。お米を干す座先に、皆、座りました。とぎれとぎれに聞こえてくる声は、私たちに何を言っているのか聞き取れません。大人たちはみな泣き出しました。
「どうしたん。どうしたん。」
「戦争に負けたんや。」
叔母も泣いていました。
「そしたらもう逃げんでもええな。もう、敵機は来んの?」
天にも昇るほどうれしかったことを覚えています。もう逃げなくてもいい。橋の下で足をぬらしながら、艦載機が斜めに撃ってきたらどうしよう。そんなことを考えなくてもいい。とにかくうれしかった。のです。9歳の子どもに、敗戦の悔しさなど微塵もないのです。
こうして戦争は終わりました。でも、生活の不自由さは相変わらずでした。鶏舎を床上げしたため、蚤が多く、毎朝100匹やっつけてから登校したこと、仕切った壁をくり抜いて1個の裸電球を2軒で使ったこと、お米ほしさに稲刈りに行って、ちきせれそうになるほど指を切ったこと…。でも、何より悲しく悔しかったことは、雨の日に学校へ行けないことでした。傘もカッパもないので、村の子どもが登校していくのを羨ましく見ているほかありませんでした。勉強だけはまけんぞと、ミカン箱をひっくり返した机で、意地を張って見せたのも悲しい思い出です。
空襲の恐ろしさは、肌で感じた者にしかわからないでしょう。しかし、戦争がいかに悲惨でおろかなものであるか。どうしても、これだけは、わが子に、生徒たちに語っておかずにはいられないのです。それは、私が、戦争の体験者であるからです。
「戦争を知らない婦人に贈る 第2集 今、語っておきたい私の体験と平和への願い」
城北支部婦人部/1987年発行/所収