あの日はもう2度と
有木 一郎(元 都島中学校)
恐怖の一瞬
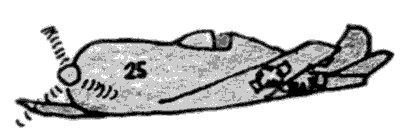
後ろから追いかけてきた機銃掃射の弾痕が、逃げまどうぼくの足もとを、砂煙をあげて追いぬいていく。頭上には、不気味でけたたましい音を立てながら、小さな機体があざ笑うように舞っている。2機、3機、4機…。米軍の艦載機(当時、関西だけを襲う関西機と思っていた)である。山へ友達と、しば刈りに行った時のことだ。米兵の顔が見える。笑っている。ジャレているみたいだ。屋根の猫も撃った。揺れる洗濯物も撃った。動いているものは、何でも撃った。行ったかと思うとまた戻ってくる。「助かった。」と思うのは甲高いプロペラ音が完全に消えた時だ。海に潜って貝を採っているときにも、こいつに狙われた。発射音とともに、岩の破片が煙を残して飛び散る情景は、思い出しただけでも身の毛がよだつ。
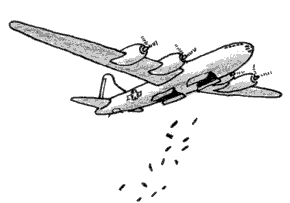
石臼で、きな粉やはったい粉を引く時のような音、五臓六腑に響きわたる鈍重な音、今も忘れることのできないB29の爆音だ。この音が聞こえてから警戒警報や空襲警報が出たものだ。その次に聞こえてくるのが、ぼくらを地面にはいつくばらせた。爆弾や焼夷弾の呪いのような落下音だ。その音で、さく裂地点の遠近が分かる。緊張の一瞬だ。こうして村の何軒かが焼失し何人かが犠牲になった。ぼくの脳裏には、今もあの、異様な、黒い物体と、4発の妖しげな怪音がはっきり残っている。
国防色
昭和11年、ぼくは、和歌山の片田舎の小学生となった。そこには、美しい海と山とがあった。2年生のころから学校や村の行事が急に多くなった。なんでも戦争に勝って日本軍が中国(当時、ぼくたちは支那といっていた)の市や町を占領したかららしい。昼は旗行列、夜は提灯(ちょうちん)行列とことあるごとに、村中が湧き立った。愛国行進曲「見よ東海の空明けて…。」という日本賛歌を得意そうに歌ったのもこのころだ。年を追うに従って「わが大君に召されたる」出征兵士を送る行事が頻繁になる。赤紙を手にした若者が村の神社で武運長久の祈願を受け、「豊葦原の千五百秋の瑞穂の国」の赤子となったこの若者達を、ぼくたちは、村のはずれの田んぼ道に並んで、見えなくなるまで小旗を振って見送った。やがて、まもなく同じように村のはずれの田んぼ道に並んで、遺族の胸に抱かれた白木の箱を「殉国勇士」と賛美して迎えた。しばらくして、村の2つのお寺には、星のついた長い墓標がいくつも建った。
ぼくはこの数年、毎日のように家で日の丸の旗を作った。当時、ことある度に、この旗が顔を出した。日の丸用のお皿は縁が赤インクや色鉛筆で真っ赤になった。
このようにして「ぼく」という国防色の虚像がつくられたのである。
配給と供出
華々しく行われた紀元2600年の行事のあと、昭和16年、ついに太平洋戦争(当時、大東亜戦争といった)が始まった。12月8日は大詔奉戴日として記念の日とされ、ぼくは、国民学校を卒業して町の中学校(旧制)に入った。
このころには既に物資不足が深刻になり、家では、売り食いの竹の子生活が始まっていた。上物好きで、ためこんだ祖母の着物が毎日のように2枚3枚と衣装びつやたんす・長持ちの中から消えていった。「銀シャリを食うやつは非国民だ。」といわれ、中学の弁当も麦主体、芋主体、海草主体のものになり、それを梅干しとともに黒ずんだ竹行李の弁当箱に遠慮がちに詰め、昼食時には、揺られて片側に冷たく寄り添っている米や麦を探したものだ。
配給制度も厳しくなる。隣組の人が集まって、マッチの棒やきざみたばこの葉を指でつまんで、古新聞の上で分けていた。炭やロウソク、塩、味噌などもあったが、砂糖の配給は全く記憶にない。しかも配給された品は少量なのですぐなくなった。当時、家の中では、火の気は絶やせない。マッチも炭もないので、火鉢に小さい生木を埋めて火を確保した。カラケシも貴重品だ。やがてつけ木(マッチ棒の火薬のかわりに硫黄を塗ったもの)の配給があった。塩の代わりに海の水を汲んできて使った。愛煙家だった祖母と母はよもぎや松葉をたばこの代わりに吸っていた。
太陽の光のある間は電気は来なかった。家には、電球のほかには電気製品(ラジオ・アイロン・こたつなど)は何もなかったから、別に不便は感じなかったが、灯火管制には少々まいった。20ワットの団らんも、警報による黒布の極度の減光で、不安のひとときに一変した。
ラジオはなかったが、新聞はとっていたように思う。町へでる飛脚が帰ってきてから届けてくれるのだから、毎日夕方になる。飛脚が休むと丸一日遅れる。記事は皇軍の戦果ばかりだ。「陥落・占領・撃墜・撃沈」等の言葉だけが、やけに印象的だった。
配給と対照的なものに、供出があった。貴金属や銅製品をお上に出せというのである。細かいことは覚えていないが、家で大切にしていた物は、ほとんど役場の人が持って行ったらしい。5、6個あった宣徳の火鉢、毎日使っていた銅のバケツ・鍋・やかん、果てはたんすの引き手から仏具まで持っていかれた。金の時計、金縁の眼鏡、金張りの総入れ歯など、祖母は涙しながら「お国のためなら」と、いとおしながら手放してしまった。半年ほどして、東条英機名義の感謝状が届いた。
それは、ぼくが大人になったとき、破って捨てた。
「君国に殉ぜん」
片道8キロの中学に通うため、50円で中古の自転車を買った。寒稽古の朝、海岸の絶壁の山道を夜明けの星明かりにかすかに見える霜の降りた馬糞をたよりに、息をはずませてペダルを踏んだ。やがて、1 年たらずでタイヤもだめになり、自転車はサビで赤くなった。それ以来、休みの日には、水平線の見える切り立った高台で、藁(わら)を打って草履(ぞうり)を作った。それは米をつくるのと同じくらい、ぼくらにとってはつらい仕事だった。中学に歩いて通うには、週に最低2、3足は要る。雨の日にはハネがあがるので、素足で走った。晴れた日には、トラックが来ると荷台の後ろにぶらさがった。大切な草履の消耗を少しでも防ぐためである。
8時半から中学の日課が始まる。柔道・剣道・教練(銃剣術)・歩調と号令をあわせたかけ足、それが1日のフルコースだ。武道館の正面にはこんな額が掲げられていた。「国は神国、道は神武、人は神人なり。純一無雑、忍苦修練、以て君国に殉ぜん。」疲れ切って8キロの道を歩いて帰るころには、夜の月が中天にかかり、朝おろしたばかりの草履もかなりくたびれていた。
10キロ装備での40キロ行軍・雨中行事・夜行軍…これが今でいう遠足だ。こんな行事があると必ず書ききれないほどのエピソードもある。ただし、その当時、修学旅行という行事は、ぼくたちには全く無縁だった。
教練の時、小銃を倒したために、頭を割られた先輩がいる。その小銃には、菊の紋が刻まれていたからだ。「恐れおおくも…」の時に笑って、真冬の運動場に全裸で立たされたクラスもあった。ぼくも奉安殿の芝生に転がっていて、冷たいプールにほうり込まれ、そのあと、恭しく礼を言わされた。
そのころから、勉強はあまりなく、校外にでることが多くなった。初めのうちは、近くの湿地帯の開墾だ。鋤やスコップを使うことが多い。ぼくは小学生の頃から田植えや稲刈りや芋堀りなど、出征兵士宅の手伝いでよくやったので、別に苦しくもなかった。おやつに20個ほどのカンパンをもらえるのが唯一の楽しみだった。
そのころ学校で、再生ゴムの地下足袋が配給になった。次は軍用道路の建設だ。山にハッパ(発破)を仕掛け、崩した土をトロッコで運ぶ。今にして思えば重労働だが、子ども心にしてはおもしろくもあった。石油の製油所にも行った。薄青く輝いた石油をひそかに水筒に入れ持ち帰り母に大変しかられた。翌日から2、3日、水筒の中のお茶の味が少し変だった。砂浜の松の根も掘った。松根油がとれるそうだ。砂浜の松の根は深い。掘っても掘っても崩れてくる蟻地獄の中の作業だ。小さい根を持って帰って燃やしてみた。ほんとによく燃えたが、家中ススだらけになったので、また叱られた。
学徒動員
(1)飛行機工場へ
いよいよ、完全に学校を離れた生活が始まった。「今こそ筆を投げうちて、勝利ゆるがぬ生産に」かりたてられたのである。学徒動員だ。中学3年だった。納屋で眠っていた例の自転車はノーパン(チューブの要らないタイヤ)をはめられて、ふたたび日の目を見た。地道では強烈な振動だ。行き先は、中学のそばの飛行機工場だ。何を作ったという覚えはないが、ただ、初めて旋盤を使わされた印象は強い。動力は天井に取り付けたシャフトからベルトを伝って機械に届くので、むずかしいベルトのかけはずしをよくやらされた。ベルトに巻き込まれて大けがをしたものもいる。バイト(旋盤の刃物)の先のダイス(鉄を切る鋼鉄)を研磨で削りすぎて大変叱られた。旋盤は、油や鉄粉や煙が目や喉に入る。服や顔にも容赦なく襲いかかる。油で黒光りした服を着て、紙の戦闘帽にゲートル姿という一群が、ノーパン自転車に揺られて急ぐ白砂青松の地の光景は、違和感あふれて、想像しただけでもこっけいだ。
(2)水盃
まもなく横浜に配置転換だ。もちろん理由などわからない。近所からは餞別をもらい、家では水盃を交わして出発した。夜の名古屋市街は猛烈に燃えていた。警報毎に列車は止まり、横浜まで丸2日ぐらいかかった。京浜急行の上大岡というところに寮があった。そこから2駅先に工場(今の石川島播磨重工)がある。空襲が激しくなると電車が走らないときが多くなり、僕たちは線路伝いに、片道4キロを歩いた。トンネル内で電車とすれ違ったこともある。工場は海軍の管理下だったので、毎朝、決まった時間に「軍艦マーチ」と「海ゆかば」が流されていた。
ぼくたちの勤務は3交代で、1週間ずつ次のローテーションで勤める。
A 6時~14時 B 14時~22時 C 22時~6時
どの時間帯をとっても、中学生には苛酷すぎた。Aのときは、帰りにトンネルの手前で野いちごを探した。Bのときは、寮のそばの畑へ芋や野菜を拝借に行った。Cの時は、今の空腹を保つために寮で横になっていた。どれも平和そうに見えるが、いずれも命がけである。月に5円か10円かの小遣いを教師からもらって、町へ芋飴を買いに行ったが、家から届いた小包は僕たちの手(口)には入らなかった。戦争に勝つどころではない。空腹に克たねばならぬ。節をつけて無造作に輪切りにした竹の食器に入った一杯の雑炊に、われ先に席を争った。食券を偽造したり、夜中に忍び込んだ食堂の残飯にむしゃぶりついたりしたこともあった。好意をよせていた女学生の宿舎にかき餅をもらいに行ったこともある。いずれも見つかって、生きて帰れないのではと思うほどの折かんを受けた。
休日には、寮で、大きな釜の熱湯に、みんな下着をぶちこんだ。パンツの縫い目にぎっしり並んだシラミの大群は、今、思っただけでも気分が悪くなる。
(3)1000分の2、3ミリ
横浜での作業は飛行機のエンジン部分の部品作りだ。主接合棒・副接合棒、それにケルメットという、いずれもプロペラの回転に重要な役割を果たす部品である。ぼくは検査係に回され、毎日、ノギスやマイクロメーターとにらめっこだ。1000分の2、3ミリが勝負である。オシャカ(不良品)が多いと叱られた。試運転の音は威勢がいい。しかし、それが飛んだのか、落ちたのか、あとのことは全くわからない。
昭和20年も、6月頃になると、昼も夜も、度々、防空壕へ避難するようになった。数百人もはいれるかという迷路のような大トンネルだ。山一つくりぬいて作ったような、広くて、不気味な感じのする薄暗い壕である。でも空一面を真っ黒に覆うB29の編隊は、異様で、とても恐ろしかった。
ぬけがら
ある日、突然、帰宅命令が出た。終戦になる少し前だった。幾つかのグループに分けられて、3日おきぐらいに、それぞれが横浜を後にした。が、どうしたことか、ぼくは、いちばん最後の班だった。空襲と飢餓と労働で身も心も完全なぬけがらになったぼくたちを乗せた、窓も座席もない貨物列車が、往きの倍ぐらいの時間をかけて、けだるそうに、西へ西へと進んだ。
和歌山に帰った翌日、先発隊のほとんどに、軍からの表彰があったが、ぼくたちには何もなかった。それからはどうなったのか、まったく覚えていない。広島や長崎に原爆が落ちたのや、敗戦の玉音放送のあったことを知ったのは、何日か後になってからである。まもなく、「天皇万歳」を叫んで、ある教師が切腹したという噂が、ぼくたちの間に流れた。
消えぬ傷跡
やがて心の傷も癒えぬままに、英語の教科書も戻ってきた。微分・積分も徒然草も伊勢物語も帰ってきた。武道館が体育館に変わって、例の「殉国」の額もおろされ、奉安殿はつぶされて、憩いの庭となった。死の銃剣術場はテニスコートに変わり、銃器庫はクラブ室に改装されて、戦後の中学生生活の息吹が聞こえ出した。ぼくは、中学4年生だった。
以来、徐々に自分を取り戻していったが、戦争で失ったものの代償は、どうしても見いだせない。確かに、ぼくたちは、戦争による貧困や苦痛に耐えてきた。規律ある集団生活も営んだ。礼儀や勤労の厳しさも経験した。しかし、これらは得たものではなく、失ったものである。戦争という名のもとに、物心ついたときから人間性を否定され、自由を奪われ、一つの旗の下に滅私奉公を強いられた副産物に過ぎない。そして、すべてのものが犠牲となり、人間を取り戻したときには、償いようのない大きな傷跡だけが、永遠に残っていた。
かといって、ぼくは今さら、少年時代や青春を返して欲しいなどとは思わない。ぼくらは、これからの若者や子どもたちに、このような悲劇の体験を2度とさせないためにも機会あるごとに、戦争の悲惨さや愚かさを訴えていかなければならない。そして今も急ピッチで聞こえてくる軍靴の音を、スクラム組んで阻止しなければならない。
城北支部女性部「戦争体験文集」第5集所収 1992年発行
(中見出しは編集部)